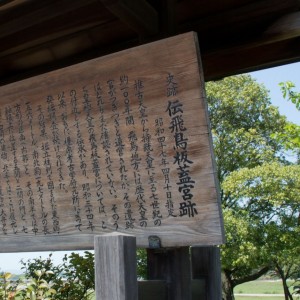二上に立つべき春のはや暮れぬ
二上山は500m足らずだから低山である。
奈良には古くからの歴史に関係する山が多く、そしてこれが大事なのだがさして高くないので山歩き、と言ってもハイキングレベルだが、に挑戦しようと最近思うようになった。
実のところ、若い頃に奥多摩とか蓑毛あたりのハイキングで音を上げたので今まで山というのは苦手意識が優っていたのだが、こんな身近に日帰りハイキングコースがいくつもあると背中を押してくれるような気がする。
登るなら最初は二上山と決めていたのだが、ずるずると今日まで。
すでに30度超えの日もあり一気に夏が来そうだというのに、ハイキング入門に最適な4月はもう終わろうとしている。