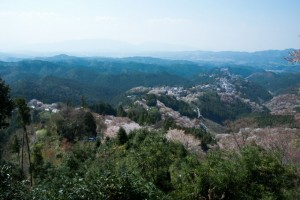床濡れるほどに砂吐く浅蜊かな
今ではアサリやシジミというのは、スーパーで買うのが当たり前となっている。
この時期になるとうまいアサリの汁を食いたくなるのだが、うちの嫁さんときたら、流通が複雑で本当の産地というのがよく分からないという理由ですっかり買ってこなくなった。
たしかに、三重産と書いてあっても最後の袋詰めしたのが三重であって、そいつはもしかしたら半島からの輸入物かもしれないのだ。
産地はともかく、複雑な流通のせいか、ぷっくらしたアサリなりシジミというのは最近は滅多に口に出来なくなったのは事実である。それに、真空パックみたいな袋詰めされ息も絶え絶えのアサリなどとても旨そうには思えない。
大粒のアサリをバケツ一杯収穫しては包丁を差し込んだ金盥で砂吐きさせるのだが、床がすっかり濡れるほど盛大な飛沫がとんだ昔の光景が懐かしい。