鹿のまり置ける芝生や冬木立

奈良公園の落葉もすっかり落ちたようだ。
すでに午後3時だが、日脚が伸びているのを実感するほど公苑には日がまだ残っている。
ここは大仏さまの講堂裏だが、どういうわけか鹿たちは煎餅くれではなく、しきりに何かを拾っているようだった。

めざせ5000句。1年365句として15年。。。
鹿のまり置ける芝生や冬木立

奈良公園の落葉もすっかり落ちたようだ。
すでに午後3時だが、日脚が伸びているのを実感するほど公苑には日がまだ残っている。
ここは大仏さまの講堂裏だが、どういうわけか鹿たちは煎餅くれではなく、しきりに何かを拾っているようだった。
霜囲いおのが力を試すなり
サヤエンドウでも蒔いたのだろうか。
霜囲いが風に煽られるたびに、20センチほど伸びた若い芽が藁の間から垣間見える。
人はほんの少し環境を整えるだけである。あとは自力で育ってゆく。
人間も植物も、逞しさとはそういうものだろう。
笹鳴きの導くままに宮参り
自転車ではなく今日も散歩が続く。
王寺側の大和川堤防を歩いていたら、こんもりした森の中を移動していく笹鳴きがある。
声に誘われ森の入り口に廻ったらそこは式内久度神社とあった。

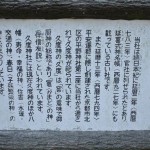
調べてみると八世紀には既にあったようだが起源は定かではなく、平安京移転の際平野神社に移されたという。
関西で「おくどさん」というように、竈の神様。
ただ、どう考えても腑に落ちない点がある。
というのは、このあたり王寺駅を中心とする一帯は三方の東から北、西へと大きく迂回する大和川に囲まれており、古代には洪水の度に陥没してしまうような低地にあるからだ。まして堤防際の、つまりかつては河原の延長のようなところに竈を祀る社を置くとは到底思えない。
どこか謎めいている神社ではある。
手袋や散歩復路の電車にて
伝説の龍田と思われる関西本線三郷駅周辺を散策。いきなり駅舎の横に能因法師の歌碑があった。
光の具合か肉眼でも読みにくかったが。

同駅から現在の龍田大社に向かって100メートルほどいくと神南備神社があった。


神南備とは神のおはすところという意味で、丘の南端麓に置かれる。
ということは、この杜に続く尾根をたぐっていくと三室山(みむろ、みもろも神南備と同義)に到達することになる。
ここを辿ってさらに留所(とめしょ)山まで登れば難波と大和を結ぶ古道龍田越えらしい。
ここで難波へ向かう人を送ったり、あるいは向かおうという旅人自身の歌が数多く残されている。
同駅から西方向へ50メートルほど、住宅団地入り口に、

犬養孝博士の書だそうだ。
ところで、「神南備」だが万葉集には龍田の神南備だけで10首はあるらしい。
虫麻呂歌碑からさらに西へ50メートルほどいった線路際に磐瀬の杜公園が移されてあり、中に一首。

なにやら源氏博士のコメントもいただけそうであるが。
このあと、龍田の滝があったと思われる亀の瀬方面へ行こうと思ったが時間切れ。おまけにくたびれたので三郷駅から王寺駅まで一駅電車で戻ることにした。
このあたり一帯はまだまだ探索する必要がありそうで、もう少し暖かくなったら峠越えの道を探そうと思う。
蝋梅の病みたるまでに肌透けて
和風の家の玄関先に蝋梅が咲き始めていた。
開いたばかりとみえて香りは届かない。花弁は一様に上向き気味で、透過光が眩しいくらい。
暦は寒に入ったが、やがて早梅も顔を見せてくれるだろう。
零下二度名に負ふ盆地の小寒かな
昨夜の9時頃には既にクルマのウィンドウが凍っていた。
もちろん今朝はどの家の屋根も霜で真っ白である。
大和盆地では冬型気圧配置が緩む朝は降りるということをローカルニュースで知って、今日あたりはと覚悟していたら案の定である。
寒さはともかく、常に厚くて黒い雲が流れピリっとした快晴がないのは関東とは大違いで、日向ぼっこといういかにも気持ちよさげな季語にはいささか遠いところかもしれない。