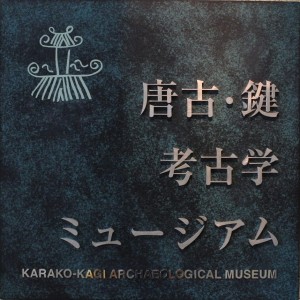愛読の書を開きをり西行忌
今日27日は旧暦2月16日で西行さんの忌日、月齢はと言うとうまい具合に15.3、いわゆる満月と重なった。
「願はくは花の下にて春死なむ そのきさらぎの望月の頃」の歌通り、今から813年前にみごと大往生。この朝なんとはなしに白州和子の「西行」を取り出してみた。
この文庫本は、引っ越しにあたってかなりの本を始末してきたのだが、またいつか読みたい一冊として残した数少ないものの一つである。考えてみれば持ってきた本というのは、一時期雑誌編集に関わった際に大きな影響を受けた先生方の著作が大半で、純文学性が高いものが多いのだが、エッセイ、紀行文など文章がすぐれていたり、文体が好きであったりしたものたちもいくつか手許に残った。言ってみれば美しくて、見事な日本語というのが好きなのであり、ましたこの歳にいたって世俗にまみれた言葉を書き連ねた本など読んだとて何の感興も得るものはなく、むしろそんなものを読んでいる暇はないと思うのだ。
自分の気に入ったものやこと、場所へだけ、喰う、見る、読む、行く。なんとぜいたくなことであろうか。